
「北海道に行ったら新鮮なウニ丼!」
そんな観光の定番グルメが、近年“高級料理”になりつつあります。
北海道・利尻島や礼文島のウニ丼は、かつて3,000〜5,000円程度で楽しめたのに、いまでは 1万5千円〜1万8千円 に達しているお店も。
なぜウニがこれほどまでに高騰しているのでしょうか?
価格高騰の背景
1. 温暖化による漁獲量の減少
近年、海水温の上昇によってウニの餌である昆布が枯れてしまうケースが増えています。
特に北海道周辺では“暖流の影響”が強まり、昆布の生育が不安定に。
その結果、漁獲量が激減 → 市場価格が高騰 という流れが生まれています。
2. 海外需要の拡大
寿司人気の高まりとともに、海外でのウニ需要も急増。
アメリカや中国では高級食材として扱われ、日本国内での価格を押し上げています。
3. 人手不足と輸送コスト
漁師の高齢化や燃料費の高騰も、価格をさらに押し上げる要因です。
地元では「漁を続けたくても担い手が足りない」という声も少なくありません。

地域への影響
北海道の観光地では、ウニ丼の値上がりが 観光客の財布に直撃。
「せっかく利尻に来たけど、1万円を超えるウニ丼は手が出ない」という観光客も。
一方で、漁業者は「そもそも獲れないから値上げせざるを得ない」と苦しい現実に直面しています。
つまり、
- 観光客 → 高すぎて食べにくい
- 漁師 → 獲れないから収入が安定しない
- 地域 → グルメ観光の魅力が薄れる
という三重苦の状態になっているのです。
家計への影響
ウニだけでなく、サケやサンマなど北海道の海産物は軒並み価格が上昇。
スーパーに並ぶ輸入ウニ(チリ産やロシア産)ですら価格がじわじわ上がり、「ウニは特別な日にしか食べられない食材」 へと変化しています。
外食産業でもウニを使ったパスタや寿司メニューが縮小傾向にあり、私たちの食卓からウニが遠ざかっているのが現実です。
今後の展望
- 養殖ウニへの期待
近年、昆布を食べさせて味を調整する養殖技術が進化。将来的には天然ウニに匹敵する味の養殖ウニが増え、価格を安定させる可能性があります。 - 観光スタイルの変化
「高級ウニ丼」ではなく、“小鉢で少量のウニを味わう” スタイルが広がるかもしれません。 - サステナブルな消費
環境問題を意識して、「旬や産地を選んで食べる」「代替食材で楽しむ」といった工夫が家計を守るポイントになります。

まとめ
ウニの高騰は「ただの値上げ」ではなく、地球温暖化・地域経済・消費者の生活 に直結した大きな問題です。
北海道の観光グルメとして親しまれてきたウニ丼が1万5千円以上する今、私たちは「どのように海の恵みと付き合っていくか」を考える時期に来ているのかもしれません。
次にウニを食べるときは、その背景にある自然や漁師さんの苦労にも思いを馳せたいですね。

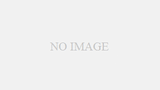
コメント